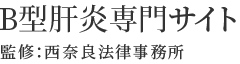B型肝炎給付金が受け取れるのはどんな人?
B型肝炎給付金受給のための要件

B型肝炎給付金の対象者は大きく「一次感染者」「二次感染者」「一次感染者・二次感染者の遺族」に分けられ、それぞれの要件は次の通りです。
一次感染者
一次感染者とは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間で、7歳までに受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)において、注射器の使い回しが原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方を言います。
一次感染者の要件
- B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染(キャリア化)している
- 0~7歳までに集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)を受けている
- 集団予防接種等で注射器の使い回しがあった
- 感染の原因が母子感染でない
- 集団予防接種等以外の感染原因がない
必要な書類
- B型肝炎ウイルス(HBV)の検査結果
6ヶ月以上の期間をあけて2回の血液検査を行ったところ、「HBs抗原」が陽性だった
6ヶ月以上の期間をあけて2回の血液検査を行ったところ、「HBV-DNA」が陽性だった
6ヶ月以上の期間をあけて2回の血液検査を行ったところ、「HBe抗原」が陽性だった
HBc抗体が高力価陽性だった
※これらのうちいずれか1つ
- 7歳までに集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)を受けた事実を証明するもの(母子手帳など)
- 過去1年の医療記録(※無症状の場合は不要)
- HBV分子系統解析検査の結果(※父子感染ではないことを証明するもの)
- 母子手帳の記録(※紛失した場合には、病院に「接種痕の意見書」を作成してもらう)
- 予防接種台帳の写し
二次感染者
二次感染者とは、一次感染者からの母子感染または父子感染(※)により、B型肝炎ウイルスに持続感染(キャリア化)した方を言います。
※平成26年1月24日より、父子感染でも二次感染者として認められるようになりました
二次感染者の要件
- B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染(キャリア化)している
- 母親が一次感染者
- 母子感染が原因でB型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染(キャリア化)した
- 母子感染以外に感染原因がない
必要な書類
- B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染(キャリア化)していることを証明するもの
- HBV分子系統解析検査の結果(※母子・父子感染であることを証明するもの)
- 診断書(※無症状の場合は不要)
- 母親・父親が一次感染者であることを証明するもの
一次感染者・二次感染者の遺族
上記の要件を満たす一次感染者・二次感染者がすでに死亡している場合、そのご遺族は国に対して訴訟提起し和解することで、B型肝炎給付金を受け取ることができます。
B型肝炎給付金の金額は?
B型肝炎給付金の請求期限は「2027年3月末」まで
B型肝炎給付金の期限は「2027年3月末」までです。これを過ぎると請求できませんので、お早めに富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所までご相談ください。
病態に応じて金額は異なります
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 病態 | 給付金額 |
|---|---|
| 死亡・肝臓がん・重度の肝硬変 | 3,600万円 |
| 死亡・肝臓がん・重度の肝硬変 ※排斥期間(死亡・発症後20年以上)が経過した場合 | 900万円 |
| 軽度の肝硬変 | 2,500万円 |
| 軽度の肝硬変 ※排斥期間(発症後20年以上)が経過して、現在治療中の場合 | 600万円 |
| 軽度の肝硬変 ※排斥期間(発症後20年以上)が経過して、現在は治療を受けていない場合 | 300万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 |
| 慢性肝炎 ※排斥期間(発症後20年以上)が経過して、現在治療中の場合 | 300万円 |
| 慢性肝炎 ※排斥期間(発症後20年以上)が経過して、現在は治療を受けていない場合 | 150万円 |
| 無症候性キャリア | 50万円+定期検査の費用など |
| 無症候性キャリア ※排斥期間(発症後20年以上)が経過していない場合 | 600万円 |
上記以外に受け取れるもの
B型肝炎給付金では、上記の給付金以外にも次の手当金が受け取れます。
- 訴訟提起にかかる弁護士費用(給付金の4%相当)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
さらに特定無症候性持続感染者(排斥期間が経過した無症候性キャリア)の方は、次の手当金が受け取れます。
- 慢性肝炎などが発症していないか確認するための定期検査の費用
- 母子感染を防止するための医療費
- 世帯内での感染を防止するための医療費
- 定期検査のための費用
「未発症なので訴訟提起しなくていいのでは?」
とお考えの方へ
今、認定されておけば後の手続きがスムーズです

現在B型肝炎が発症しておらず、自覚症状がなくても、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染していることに変わりはありません。そのため、将来的に慢性肝炎などを発症する可能性があります。その時になって訴訟提起しようと思っても、年齢や健康面で大変な負担になることもありますので、元気なうちに訴訟提起して認定を受けておくことをおすすめします。
「無症候性キャリア」として認定されておけば、慢性肝炎などが発症した場合でもスムーズに手続きでき、病態に応じて給付金が追加で受け取れます。
一次感染者の方はお母様が元気なうちに手続きしておきましょう
これはB型肝炎給付金に限らず、法律トラブル全般に言えることですが、時間が経過すればするほど請求しにくくなります。B型肝炎給付金では、一次感染者の方は特に注意が必要です。
一次感染者であること認めてもらうためには、「感染の原因が母子感染でない」という要件を満たす必要がありますが、もしお母様がお亡くなりになっていたり、危篤状態にあったりすると、これが困難になります。なので、一次感染者の方は、お母様が元気なうちに手続きされておくことをおすすめします。
「給付金を受給した後に病態が悪化した」という方へ
追加給付金の請求ができます
追加給付金の請求とは、B型肝炎給付金の支給を受けた後、病態が進行した時に、進行前の病態に応じて国から受け取った給付金と、進行後の病態に応じて受け取れる給付金の差額を請求することです。
肝臓は「沈黙の臓器」ですので、自覚症状がないまま進行し、悪化してしまうケースが少なくありません。また、無症候性キャリアと慢性肝炎の線引きは非常に難しく、医療記録を見てみないと判断できません。ご本人は無症候性キャリアと思っていても、もしかしたら慢性肝炎であるかもしれないのです。これはご自身で判断できることではありませんので、専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
追加給付金の請求では「訴訟提起」は必要ありません
「追加給付金を請求するのに、再度、訴訟提起が必要なのでは?」とご心配な方もおられると思いますが、ご安心ください。追加給付金の請求では訴訟提起は必要ありません。前回の請求時よりも手続きが簡便でスムーズですし、一度当事務所のサポートを受けていれば、必要な資料が揃っているので少ない負担・短期間で請求可能です。
追加給付金が請求できるのは「病態の悪化を知ってから3年以内」
追加給付金の請求には期限があり、ご本人が病態の悪化を知った日から3年以内となっています。かかりつけの医師から「病態が悪化している」と言われた方は、お早めに富雄・生駒・学園前の西奈良法律事務所までご相談ください。
追加給付金の受給例
前回の請求時に「慢性肝炎」と認定された方が、病態が進行して「肝臓がん」になった場合、慢性肝炎の給付金1,250万円と肝臓がんの給付金3,600万円の差額、2,350万円を受け取ることができます。